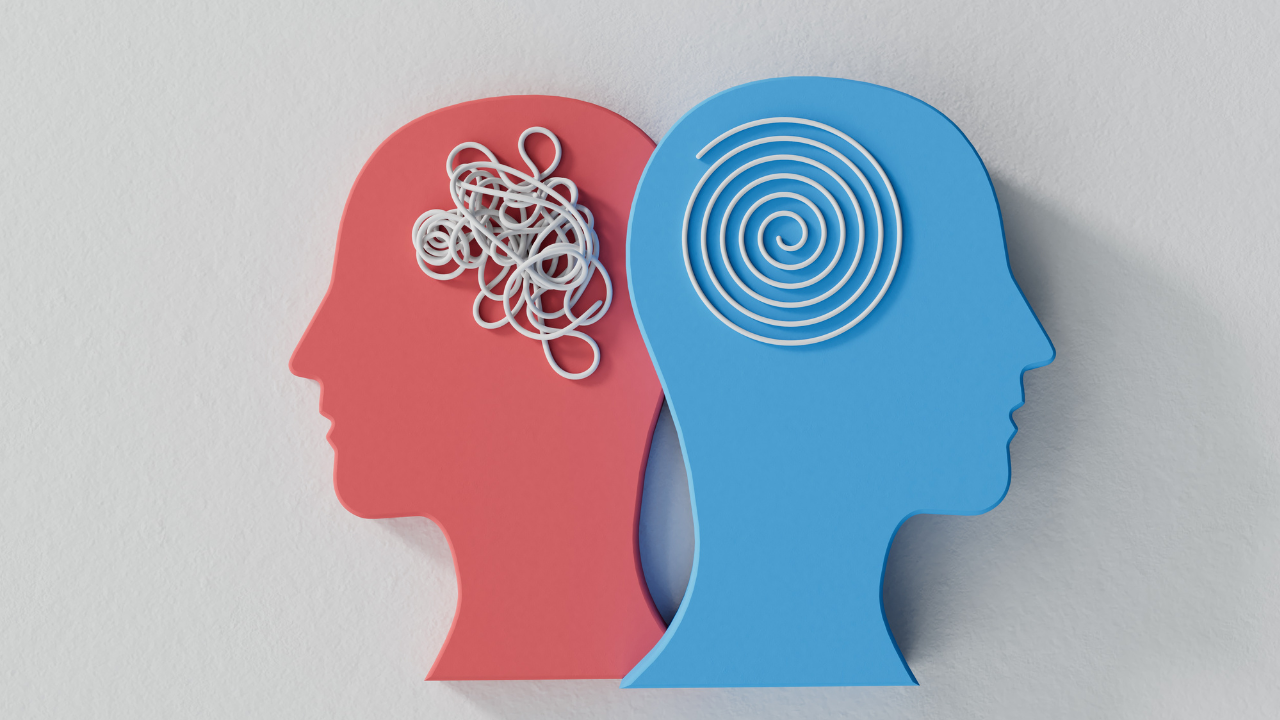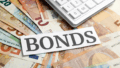これまで、ゼロクーポン債と利付債について教えてもらったんですけど、どちらも魅力的に感じています。

そうよね。ゼロクーポン債と利付債には、どちらも一長一短があって、どちらを選べばいいか悩む人も多いのよ。

そうですよね。資金がたくさんあれば両方やってみてもいいと思うんですけど、両方やる余裕がない場合は、どっちを選んだらいいんでしょうか。

それでは今回は、あなたに合った債券選びの方法を解説するわね。
私が資産運用を始めて一番最初に購入したのが債券でした。まだ大学生の頃です。
そして真っ先に悩んだのが「どんな債券を買うべきか?」ということでした。
まずは証券会社で証券口座を開設して、さっそく債券を調べてみると、出てくるのが「ゼロクーポン債」と「利付債」でした。正直、この違いがよく理解できませんでした。
そして最終的に、結局どっちを購入したらいいの?となりました。
そこで今回は、ゼロクーポン債と利付債、あなたに合った債券選びの方法を解説していきます。

ゼロクーポン債と利付債の基本理解
まずは、ゼロクーポン債と利付債について、どういう特徴のある債券なのかを見ていきましょう。
ゼロクーポン債とは?
ゼロクーポン債とは、利息が一切支払われない債券です。その代わり、額面よりもかなり安い価格で購入できます。
例えば、額面100万円の債券が60万円で購入できたりします。
保有している間、一切利息は受け取れませんが、満期時に額面金額の100万円が返ってきます。
要するに、満期まで保有すれば100万円-60万円=40万円の利益が出るということです。
満期までの期間が10年だとすると、60万円の投資に対して10年間で40万円の利益が出ることになるので、単利で計算すると4%の利回りで10年間運用できたことになります。
満期までの間、利息を一切受け取れないので、キャッシュフローは発生しませんが、最終的な利回りで見ると悪くないと感じるのではないでしょうか。
利付債とは?
一方、利付債は定期的に利子が支払われる債券です。
例えば、利率3%の債券を100万円購入すると、年2回、1回あたり15,000円(税引き前)の利子を受け取ることができます。
そして、満期まで保有すれば元本が戻ります。定期的にキャッシュフローを得ることができるので、資産計画が立てやすく、何かの支払いにあてたり、自分の楽しみの為に使ったりすることができます。

ゼロクーポン債の特徴とメリット
それではゼロクーポン債について、特徴とメリットを見ていきましょう。
利回りの計算方法
期間10年、額面金額100万円のゼロクーポン債を60万円で購入したとしましょう。
満期まで保有した場合の利回りを単利で計算すると、
(100万円―60万円)÷10年÷100万円×100=4%
の利回りとなります。
10年間利息を一切受け取れないので、複利で計算する方法もありますが、今回は分かりやすく単利での計算としました。
税制上のメリット
ゼロクーポン債の税金は、満期時に購入額との差額に対して20.315%の税金がかかります。
前述の通り、額面100万円の債券を60万円で購入した場合は、差額の40万円に対して20.315%の税金がかかることになります。
よって、ゼロクーポン債は、満期時に利益が出た時点で課税されるため、課税の繰り延べ効果があります。これは長期的に運用するうえで見逃せないメリットです。

利付債の特徴とメリット
では次に、利付債の特徴とメリットをみていきましょう。
定期的な利息収入の魅力
利付債には年2回の利息の支払いがあります。
年2回の利払いがあると、生活設計がしやすくなります。
特にインカムゲイン(継続的に受け取れる収益)を重視する人には、心強い存在なのではないでしょうか。実際、ゼロクーポン債より利回りが低かったとしても、定期的な収入を得ることができるという点で、心理的には安心感があるかもしれません。
流動性の高さ
利付債の中には流動性が高いものも多く、市場価格での売却も比較的容易です。
急に現金が必要になった時に、すぐに売れるという安心感は見逃せません。
一方で、ゼロクーポン債ですと、途中で売却しようと思った場合、市場金利次第では大きく目減りするリスクがあります。

ゼロクーポン債と利付債の比較
それでは、ゼロクーポン債と利付債、どちらが良いのでしょうか?
これは債券購入の「目的次第」です。
それぞれの特性を、心を落ち着けて比較してみると、選択のヒントが見えてくるのではないでしょうか。
リスクとリターンの観点から
まずは、リスクとリターンの観点から考えてみましょう。
ゼロクーポン債は価格変動に敏感です。特に金利が上昇局面にある場合、途中売却をした際には価格が大きく下がります。ただし、満期まで保有すれば、リターンは確定します。
一方で、利付債は定期的な利子収入がある為、金利が下降局面でも一部リスクヘッジが効きます。
投資目的による選択基準
債券購入の目的が、将来、数年後の支出に備えたものであれば、ゼロクーポン債が良いでしょう。外貨建てのゼロクーポン債の場合は、満期時の為替レートによって戻ってくる金額が左右されてしまいますが、購入時点で為替レートの損益分岐点を出しておくことで、一定のリスクヘッジはできます。
一方で、現在の収入を補完する目的なら利付債が良いでしょう。利回り重視といえども、やはり定期的に収入を得られるというのは、とても安心感があります。
普段のお給料だけではあまり贅沢ができない場合でも、利子収入が入った時だけは、美味しいものを食べに行ったり、趣味に使ったりと、楽しみの為に使うこともできて、心に余裕が生まれます。

どちらが得か?投資シミュレーション
それでは、実際お得なのはどちらなのか、具体的なシミュレーションを通じて、実質リターンを比較してみたいと思います。
長期保有時のシミュレーション
【前提条件】
- 10年満期
- ゼロクーポン債:額面100万円、購入価格60万円
- 利付債:額面100万円、年利4%
【結果】
10年後の満期まで保有した場合は
- ゼロクーポン債の利益:40万円(税引き前)
- 利付債の総利息収入:40万円(税引き前)
利益だけ見ると40万円という同じ利益に見えますが、投資金額をみると、ゼロクーポン債は60万円に対して、利付債は100万円となるので、ゼロクーポン債は100万円との差額40万円を、別の方法で資産運用することが可能となります。
ということで、この差額の40万円を別の方法で運用し、それがうまくいけば、利付債よりも多くのリターンを得られる可能性があるのです。
短期売却時のシミュレーション
【前提条件】
- 10年満期
- ゼロクーポン債:額面100万円、購入価格60万円
- 利付債:額面100万円、年利4%
- 保有期間:3年で途中売却
- 途中売却時に市場金利が上昇している
市場金利がどれぐらい上昇しているかによって、途中売却時にいくらになるかが左右されますが、ゼロクーポン債は売却時に市場金利が上昇していると、売却価格が大幅に下落しやすいという特徴があります。
一方で、利付債も途中売却時には市場金利に影響されるものの、多少売却価格が下がっても、これまで受け取った利息で多少はカバーできます。その為、短期の売却かつ、売却時の市場金利が上昇していた場合は、利付債のほうがリスクが小さいといえるでしょう。
一方で、途中売却時に市場金利が下がっていた場合には、利付債の方が利益を得やすいかもしれません。

投資家のニーズに応じた選択
それでは、どういう人にはゼロクーポン債が良くて、どういう人には利付債が良いのかを見ていきましょう。
リスクを抑えたい人向けには利付債
退職金の運用や、生活資金の保全を考えるなら、やはり利付債だと思います。
定期的に利息を受け取れるというだけで、資金計画はずっと立てやすくなります。
高リターンを狙いたい人向けのはゼロクーポン債
まとまった資金を将来に備えて運用したいなら、ゼロクーポン債が良いでしょう。
途中売却をする場合は、市場金利にかなり左右されてしまいますが、満期まで保有することを前提にすれば、利付債よりも大きいリターンが見込める可能性が高いです。
また、前述のとおり、同じ額面の債券を購入する際において、ゼロクーポン債の方が元手が少なくてすみます。そうすることで、浮いた資金を別の資産運用に回すことができるので、さらなる利益を獲得できる可能性が高くなります。

ゼロクーポン債と利付債の今後の展望
ゼロクーポン債と利付債の今後の展望についても考えてみましょう。
最近の金利動向を見ていると、債券市場は再び注目を集めつつあります。
金利動向と市場の影響
金利が上がると、ゼロクーポン債の価格は下がります。逆に、金利が下がれば価格は上がります。
特に、アメリカでは利下げが期待されているので、この機会に米ドル建のゼロクーポン債を購入しておくのが良いかもしれません。
また、利付債は定期的に利息を受け取ることが出来るので、市場金利の上昇・下降の影響はやや緩やかではあるものの、やはり価格変動は避けられません。
経済状況に応じた投資戦略
インフレが進む時期には、短期の利付債が有利だといえるでしょう。
インフレが進むと、一般的には市場金利が上昇します。その為、金利が上昇した債券を買い直す為にも、短期で満期を迎える債券を保有していることが得策になります。
一方で、金利が落ち着いている局面では、長期のゼロクーポン債が狙い目になるでしょう。
途中で売却しても、損失が出る可能性が少ないうえに、満期まで保有すれば確実に額面金額を受け取ることができます(発行元が破綻しない限り)。
この為、経済ニュースをこまめにチェックし、どちらの債券を保有した方がいいかを見極めることが大切になってきます。

まとめ
ゼロクーポン債と利付債は、どちらが優れているかではなく、「どちらが自分の目的に合っているか」を考えることが大切です。
リスク、リターン、税制、流動性、それぞれの特徴を、自分の生活に照らしあわせてて考えることが大切です。
実際、私自身はゼロクーポン債と利付債を組み合わせて保有しています。やはり、どちらにも一長一短があるので、どちらか片方だけで運用するという選択肢はありませんでした。
分散投資しながら、ライフイベントに合わせて資金を動かせる設計にしておくことが重要です。
ただし、債券は最低購入単価がNISAの100円からと比べれば高く設定されています。
その為、まずはどちらかから始めるというのも一つの手です。
その場合は、まずは自分にどちらが合っているかを考えて、そちらを購入してみましょう。
最終的に重要なのは、「自分で判断する力」です。
SNSにあふれている情報を鵜呑みにせず、自分で考えて、納得のいく選択ができる力を身につけましょう。